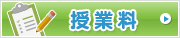逆計算 10/30(火)
数学でも理科でも公式は覚えるだけでなく、使えるようにしないといけません。また、何故そのような公式になるか疑問を持つことも大事ですが、とりあえずこれが公式と示されたものを受け入れて覚えてしまいましょう。
さて、例えば理科から「密度の公式」密度=質量÷体積というのがありますが、密度の公式だからといって、密度だけ求められるようになってもいけません。
密度と体積がわかっていれば、質量が式から求められますし、密度と質量がわかっていれば体積が求められます。
関数の「変化の割合の公式」変化の割合=yの増加量÷xの増加量からも変化の割合だけでなく、yの増加量もxの増加量も求めらるようにする必要があります。
(密度・質量・体積)もしくは(変化の割合・yの増加量・xの増加量)の3つの要素のうち、2つがわかっていれば、求めたいものを「x」と置くと、方程式が作れます。
また、公式は一方通行ではなく、逆計算もできるようにしておきましょう。
(a+b)2=a2+2ab+b2
これは、(a+b)2→a2+2ab+b2
a2+2ab+b2→(a+b)2
どちらからも変形できるようにしないといけないです。
また、これは公式ではないですが、例えば、連立方程式(y=3x+6、y=5x-8)を代入法を用いて、3x+6=5x-8と式を作れる人は多いと思います。
でも、いきなり「3x+6=5x-8」を「y=3x+6とy=5x-8」と2つの式に分解できる人は中学生では少ないと思います。(中学数学ではほとんど使わないので)
でも理屈は理解できますよね?公式に限ったことではないですが、いつも逆計算は意識しておくと良いです。ゴールからスタートを考える思考は数学でよく使います。