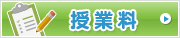中学2年生 数学 一次関数 動点 10/29(水)
一次関数はあまり好きではない人にとって文章問題、特に動点の問題は嫌いという人は多いと思います。
今回は動点の問題の解き方を一緒に学習しましょう。
問題「AB=4cm、AD=6cmの長方形ABCDで、点PはAを出発して、辺上をB、Cを通ってDまで動きます。点PがAからxcm動いたときの△APDの面積をy㎠とするとき、点Pが①辺AB上、②辺BC上、③CD上を動くときのxとyの関係を表す式とxの変域を求めましょう。」
まず四角形ABCDを描いてくださいね。
手順1:各頂点のx、y座標を求める。
手順2:辺AB上に点Pがいるときの式は頂点AとBの座標を「y=ax+b」の式に代入してa, bの値を連立方程式で求める。
それでは手順1より、各頂点の座標を求めましょう。頂点Aに点Pがいるときは、まだスタートしていないので、座標は(0,0)です。
頂点Bのx座標はAB=4cmより4,y座標は△ABDの面積です。辺ADを底辺とすると辺ABが高さになるので、6×4×1/2=12です。B(4,12)
頂点Cのx座標はAB+BC=10cmより10、y座標は△ACDの面積なので、辺AD×辺CD×1/2=12になるので、C(10、12)
頂点Dのx座標はAB+BC+CD=14cmより14。点PがDの位置に来ると、線分AP(D)のようにPとDが重なり三角形が作れないので、面積は0になります。D(14、0)
準備ができたので、手順2で①、②、③を解いていきましょう。
①点Pが辺AB上にいるときは、頂点AとBの座標をy=ax+bに代入して方程式を解きましょう。
A(0,0)を代入するとb=0。B(4,12)を代入すると、12=4a+b。b=0なので、a=3、よってy=3x
xの範囲は0≦x≦4です。
②点Pが辺BC上にいるときは、頂点BとCの座標をy=ax+bに代入して方程式を解きましょう。
B(4,12)を代入すると、12=4a+b。C(10,12)を代入すると、12=10a+b。連立するとa=0、b=12となるので、y=12
xの範囲は4≦x≦10です。
③点Pが辺CD上にいるときは、頂点CとDの座標をy=ax+bに代入して方程式を解きましょう。
C(10,12)を代入すると、12=10a+b。D(14,0)を代入すると、0=14a+b。連立するとa=-3、b=42となるので、y=-3x+42
xの範囲は10≦x≦14です。
まとめると
①の答えはy=3x(0≦x≦4)
②の答えはy=12(4≦x10)
③の答えはy=-3x+42(10≦x≦14)
式とxの変域がわかればグラフも描けます(^^)/