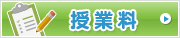問題 11/29(水)
中学生になれば、数学で本格的に文字を使っていきます。
文字ってとても便利で、「nを整数とすると」と一言断っておくと、すべての整数を「n」の一文字で表せてしまうんですね。すごいですね、感動ですね。
それでは今日は文字を使った問題について、いくつか見ていきたいと思います。
中学1年生の模試からです。
問題1、aは正の数、bは負の数で、その和が負の数であるとき、a、b、-a、-bを大きい順に並べなさい。
この問題を解くポイントとしては、文字のままで考えるのではなく、文字を適当な数字に置き換えるとわかりやすくなることです。
aは正の数、bは負の数で、その和が負の数という条件から、例えばa=1、b=-2に置き換えます。aとbを足せば、「-1」で、和が負の数になるのでOkですね。
あとは、a=1、b=-2をa、b、-a、-bに当てはめていくと、a=1、b=-2、-a=-1、-b=2となります。
以上の結果から大きい順に並べると、答え、-b>a>-a>bになります。
それではもう1問。
問題2、aは正の数、bは負の数のとき、a、b、a+b、aーb、b-aを大きい順に並べなさい。
今度の問題は、aは正の数、bは負の数という条件だけなので、a=1、b=-1に置き換えてみましょう。文字を数字に置き換えるときは、できるだけ簡単な数字にすると計算が楽になります。
そうするとa=1、b=-1、a+b=0、aーb=2、b-a=-2になるので(計算は省略しましたが大丈夫ですよね)答え、aーb>a>a+b>b>b-a