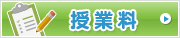30年度 入試問題 国語 3/10(土)
国語は大問数は例年通りでした。最初に「解答上の注意」がありましたが、しっかり読んでから答えられたでしょうか?
[問題一]は小問集合です。問一は漢字問題でしたが、特に難解な漢字はありませんでした。問四は毎年出題されている返り点の問題です。返り点はほとんどレ点と一.二点だけなので、少し練習すれば県立レベルの問題はすぐにできるようになります。
問五は「スピーチ原稿」を読んで問いに答える問題で、ちょっとした読解問題でした。原稿自体が結構な長文だったので、少し時間がかかったかもしれませんが、きちんと読めば答えられたと思います。
[問題二]は論説文が来ることが多いですが、今年は物語文でした。本文が見開き1ページ、次の見開きで問一から問六まであり、これで終わりかと思いきや次のページに問七として、この物語文についての生徒同士の会話文が始まるという今まで古文ではありましたが、小説文では初めてのパターンだったので、戸惑った人がいたかもしれません。そして、[問題二]が解き終えるのに時間もかかったと思います。
[問題3]は論説文でした。第一、二段落で「現代空間の多孔化」や「空間的現実の多孔化」、「空間的現実の非特権化」など???なワードが次々と出てきていやになりますが、そんなときは最終段落を読みましょう。そうすると、第一、二段落と共通する「情報」というキーワードが読み取れると思います。そうすれば、この文章は何かしら情報に関することを書いているのだなと考えると幾分読みやすくなったのではないでしょうか?
問一は接続語の空欄補充問題です。空欄Ⅰの後ろの文章を読むと、「~のような」とあります。ここから、選択肢は「あたかも」や「まさに」に絞れます、空欄Ⅱの前後の文から異なる内容が読み取れるので、ここは逆接の「しかし」が入ります。よって「あたかも」と「しかし」がセットになっている選択肢が正解です。
問二は傍線部と同じ内容を選択肢から選ぶ問題でした。傍線部があれば、その部分を含む一文すべてに線を引きましょう。そして、指示語が含まれていればその内容を必ず確認しましょう。問二の傍線部をのばすと、「こうした現象は~」から文が始まります。指示語があるので、こうした現象がどういった現象かを直前の文から探していけば、すぐに見つかり、そしてそれが答えと一致します。
問四、五は抜き出し問題です。基本的に読解問題は問題文の中にヒントになるキーワードがあるので、問題文を本文以上にしっかり読むことが大事になります。キーワードが見つかればあとは本文からそれを探せば良いだけです。
問六は段落どうしの関係を考える問題でしたが、ここは消去法でクリアできたと思います。アは対比する具体例が×、イは結論を述べているが×、ウは根拠をあげて反論しているが×、とあきらかに選択肢の中に間違いがあるので必然的に「エ」が正解と判断できます。
[問題四]は古文でした。問題数が多く、問題三の問八の作文を書き終えた所で時間になってしまった生徒もいたようです。問一は歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すというこれも毎年出題されている形式だったので、過去問で練習している人はできたでしょう。
問三の主語を答える問題や問四の会話部分を答える問題は古文ではよく出る形式です。主語は省略されることが多く、現代文と違い古文には会話部分に「 」がついていないからです。日頃から誰の動作で誰のセリフなのかに着目して古文を読むようにしましょう。
全体的には易しかったかなという印象です。ただ、いかんせん問題量が多かったので難しく感じた生徒もいるかもしれません。これからは多くの情報を短い時間で適切に処理できる力が必要となっていきます。