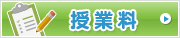30年度 入試問題 社会 3/12(月)
社会は地理・歴史・公民と3題に分けて出題されました。地理・歴史については易しかったのですが、公民はやや難しかったです。
[問題1]の地理は赤道の位置を選ぶ選択問題から始まりました。これは楽勝ですね。
問1の(3)、(5)の選択問題は、2択まで絞れてそこから悩んだ人が多かったと思います。(5)は世界の六大陸の気候帯の面積の割合について、オーストラリア大陸にあてはまるものを選択する問題でした。
ア~カの選択肢のうち、まず「亜寒帯」は南半球に存在しないという理由からア・イが消去できます。また、カも寒帯100%とあるので、南極大陸と判断でき、消去します。
ウは熱帯の割合が六割を超えているので南アメリカ大陸です。残ったエとオのどちらがオーストラリア大陸を選ぶことが難しかったですね。ちなみにもう一つはアフリカ大陸であることがわかっていれば、熱帯の割合に着目して、赤道が通っているアフリカ大陸の方が熱帯の割合が高いと判断して、オが正解と導けます。
問3は「カルデラ」や「地熱発電」、「ハザードマップ」など語句を答えさせる問題が多かったですが、いずれも基本的な語句問題だったので正答率は高くなるでしょう。
[問題2]は歴史でした。問題形式は例年通りで、苦手な生徒が多い戦後についての問題が少なかったこともあり、解きやすかったのではないでしょうか。
問1は与えられて資料について答えていく例年通りの問題でした。(1)は「712年におかれていた都」から平城京が選べました。(2)は「浄土信仰が広まった時期」ということから平安時代と判断し、平安時代の建造物である平等院鳳凰堂(写真A)-藤原頼通の組み合わせである選択肢アを選べたと思います。
歴史も例年より、選択問題より記述問題の割合が少し高かったですが、「蔵屋敷」「米騒動」といった基本的な語句を問われていたので難しくなかったと思います。
また、選択問題も時代の大まかな流れを把握していれば、出来事の年号をきちんと覚えていなかったとしても、答えられた問題が多かった印象です。
[問題3]の公民では、為替や税の種類、三権分立についての基本問題でしっかり正解しておきたいです。円安になれば輸出産業にとってなぜ有利になるのか、丸暗記でなく為替のしくみを理解していれば迷うことなく答えられたはずです。
問1の(1)は知識がなくても、与えられていた表と選択肢を照らし合わせて見るだけで答えられる問題でした。
問2の(3)の衆議院議員選挙の投票所に投票箱が3つ設置されている理由を記述する問題は難易度が高かったです。小選挙区比例代表並立制の語句は出てきたと思いますが、国民審査(衆議院議員選挙の際、最高裁判所裁判官に対して国民が投票で審査すること)が思い出せない、または覚えていなくて書けなかった人が多かったと思います。
問3の(3)の答えは「人間の安全保障」です。これは、公民分野でも一番最後の方に出てくる語句です。基本的に公民は3年生で習うので、内容を覚えている人が多いのですが、学年末が終わった以降に学習した単元については、定期テストもないので、しっかり復習(自分で勉強)ができていない単元になりがちです。受験勉強では地理と歴史に時間を割くので、なかなか公民の最後まで手が回る人は少ないでしょう。
ですので、この最後の問題は難しかったです。
30年度も図や資料、表、文をふんだんに使ったボリュームのある問題でした。ただ、昨年のような知識だけでなく思考力も試されるような問題や地理・歴史・公民分野の融合的な問題が少なかったです。しかし、これからはそのような問題が増えてくるので、さらに基本を大事にして応用問題に対応できるようにしていきましょう。