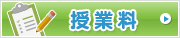県立入試理科問題予想 2/22 (金)
前世が占い師であった塾長が県立入試の理科の出題単元を予想します。
まず、これは予想でも何でもないですが、2年の化学変化もしくは3年の水溶液とイオンの単元は必ず出題されます。教科書に載っている化学式やイオン式をきちんと暗記しておきましょう。対策としては、毎年大問で出題されているので、過去問で各年度の化学変化・イオンの問題だけ解いていきます。化学反応式(原子の数合わせができるように!)や質量の計算(比例式を使いこなせること!)など解けるようにしておきましょう。
続いては「力と圧力」です。一昨年は「光」、昨年は「音」が出題されいます。これは順番的にも今年は出題されるでしょう。圧力は単位に着目して求められるようにしておきましょう。単位は「N/㎡」です。
問題では「cm」で書かれていることが多いので、単位換算をする必要があります。ちなみに、1㎠=0.0001㎡なので、覚えておいてください。単位関連では、「重さはN」で「質量はg、kg」なので押さえておいてください。
あとは、水圧と浮力の違いも理解して自分で説明できるように。
次は「地震」です。地震の単元は3年周期で大問で出題されています。問題の会話文の中で、2016年の鳥取中部地震に触れるような文章もあるかもしれません。
地震といえば、P波・S波の速さの計算です。単純に速さを求めるような問題もあれば、25年度の緊急地震速報を題材としたような応用問題も出るでしょう。まずは、2つの地点から距離と時間を求めて速さを導けるように練習しておきましょう。あとは、震源からの距離と初期微動継続時間は比例していることも覚えておくこと!グラフの問題が出ますよ!
最後は「植物の分類」です。1年生の教科書52ページ図46(植物のなかま分け)を覚えておくと良いです。
種子をつくらない植物に分類される「シダ植物」と「コケ植物」は葉・茎・根の区別の有無、維管束の有無に着目して覚えてください。
また、シダ植物は「前葉体」、コケ植物は体を地面に固定する役目の「仮根」や「雄株」・「雌株」といった語句も教科書の図を見て覚えておきましょう。
こんな感じで予想してみましたが(1年生の範囲ばっかりやな)、あくまで参考程度に・・・予想しておいてなんですが、全体をバランスよく学習してくださいね。教科書を使いながら、問題集はたの理でも整対でも普段から使っているもので練習してください。