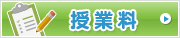解き直しは自分で 12/19(木)
過去問の解き直しは間違えた問題をすぐに解説するのではなく、まずは生徒に過去問に載っている解説を読むなどして解き直しをさせます。解説を読んで理解できればそれでOKですからね。
もちろん本当にわかっているか確認はしますけども。
わからない、間違えた問題をすぐに質問する習慣がついてしまうと自分で考えなくなりますし、また一人で勉強する、問題を解決する力が身につきません。
ですので、まずは自力で、それでもわからなければ講師に質問するようにさせています。
また、社会に関しては過去問の解説プラス問題の解き方、考え方を記述したちょこっとしたメモを渡しています。
こんな感じです↓
2019年度 社会
[問題1]
問1
(1)南アメリカ大陸はブラジルとアルゼンチンを押さえておきましょう。アルゼンチンの特徴としてパンパ(草原)を覚えておくこと。アはドバイ、イはロシア、エはアフリカのどこか
(2)日本の対せき点(地球の反対側)はアルゼンチンの東に位置する大西洋。
緯線と経線の区別は「よこいけいた」で覚えておこう。横の線が緯線、経線は縦。
(3)北半球と南半球では季節が逆になります。オークランドのあるニュージーランドの気候帯はほぼ温帯です。
問2
(1)タンカーはどのようなものを運ぶかに着目して考えてみよう。
日本のエネルギー資源の輸入相手国で押さえておくべきもの。
・石炭・鉄鉱石のNo1はオーストラリア
・原油のNo1はサウジアラビア
(2)BRICSは5か国の頭文字から成りますが、BRICSのSは最初は複数形のSで、のちにSouth AfricaのSとなり
ました。
(3)アはイタリアでピザ、イはフィジーでロボ料理、エはメキシコでタコス
問3
(1)東北地方の6県全て言えるかな?青森はリンゴが有名ですが、さくらんぼと言えば!
(2)グラフや表の問題は極端な数字(一番大きい数字や小さい数字)に着目して考えよう。愛知県といえば中京工業地帯がありますね。ア・イ・ウ・エそれぞれの1位の品目を比べるとわかると思います。
(3)正しい選択肢を選ぶ問題は間違い探し!つまり消去法で考えよう!日本の発電量の割合の問題のポイントは
2013年です。東日本大震災の影響でこれ以降原子力発電の割合が小さくなります。
水力発電はダムを利用するので、山間部に水力発電所が造られることも押さえておこう。
(4)中部地方なので、果樹栽培or米の二期作、渥美半島は何県、房総半島は何県?ちなみに半島の定義は三方を海に囲まれていることです。
問4
(1)地形図は上が北、下が南、右は東、左が西であることを押さえておく。
(2)縮図から実際の距離を求める計算は「縮図中の長さ×縮図の分母(2万5千分の1であれば、2万5千をかける)」
今回の問題であれば、4cm×25000=100000cm→1000m→1km
つまり、1辺が1kmの正方形だから・・・
[問題2]
問1
(1)この時代日本は遣唐使を派遣していました。ですので・・・
(2)ア:枕草子は清少納言、イ:平家物語は鎌倉時代、ウ:徒然草は室町時代、ちなみに枕草子・方丈記(鴨長明)・徒然草を日本三大随筆と呼びます。
(3)鎌倉・室町・江戸それぞれの幕府のトップは将軍ですが、No2の役職の名称が違うので覚えておきましょう。
鎌倉幕府は「執権」、室町幕府は「管領(かんれい)」、江戸幕府は「老中」
(4)図を見たらわかります。そのまま答えましょう。
(5)今でいう条例みたいなものです。戦国大名が自分の支配する土地のルールを決めたのですね。
(6)江戸の三大改革は良く出題されるので、誰が実施したのかその内容もセットで覚えておきましょう。
御成敗式目と武家諸法度は混同しやすいので注意です。御成敗式目は鎌倉時代に武士が初めて作ったルールです。「ええじゃないか」は幕末に起こった運動です。
問2
(1)武家諸法度は大名を統制するためのルール。3代将軍家光によりこの武家諸法度に参勤交代が追加された。
(2)教科書にも載っている絵です。「石」に着目して、革命後どのような社会になったかを考えてみよう。
(3)地租改正は記述問題でも出題されるので、その意味をしっかり説明できるようにしておこう。ポイントは年貢から現金で納めるようになったこと、地価の3%(その後2.5%)を納めたことです。
(4)1925年は治安維持法以外に普通選挙法、そしてラジオの全国放送が始まったことを覚えておこう。
満州事変、簡単に言うと暴走した関東軍(日本の軍隊)が日本の満州鉄道を爆破してそれを中国がしたとでっちあげた出来事。当時首相であった犬養毅が世界に対して「これうちがやりましてん」と世界に発表しようとしたが、犬養お前は甘いと暗殺された。これが「五・一五事件」、その後国際連盟の調査で日本の自作自演がばれたが、日本は逆切れして、国連を脱退。その後日本で軍部によるクーデターが起こる。これが「二・二六事件」、クーデターは失敗に終わるが、これ以降軍部の影響力が強くなり、戦争へと向かっていく。
(5)ア:財閥解体は戦後直後の話
イ:朝鮮戦争は一九五〇年
ウ:貿易摩擦は一九七〇年代。
[問題3]
問1
(1)議会の解散や首長の解職などは職を失うことになるので、有権者の3分の1以上が必要。3分の2以上が必要
なときは憲法改正のときのみ。
(2)①例えば、海を埋め立てるとその後どのような影響があるかなどを調べること。
②京都議定書でルールは決められたが、義務があったのは先進国のみで発展途上国に義務はなかった。
問2
(1)選挙の4原則を覚えておこう。
(2)内閣不信任の決議が可決されると、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しないといけない。
(3)PL法以外にもクーリング・オフ制度や消費者契約法など消費者を守る法律を覚えておこう。
問3
(1)ア:WHOは世界保健機関、ウ:UNICEFは国際連合児童基金(世界中の子供たちの命と健康を守るため
の機関、エ:NGOは非政府組織。非営利組織のNPOと混同しないこと。
(2)異文化理解が求められ、その結果多文化共生につながる。
(3)女性のデータに着目して考える
問4
(1)利益を追求するだけではだめですよということ。
(2)詳しくは授業にて
(3)寡占と独占の違いを理解しよう