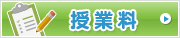30年度 入試問題 理科 3/9(金)
まず、大問がそれぞれ見開き1ページにまとまっており、ページをめくってあちこちいく必要がなかったので、その点ではとても解きやすかったと思います。
では、[問題1]からみていきましょう。問1は過去問にも出ていましたね。接眼レンズは短いほど、対物レンズは長いほど倍率が高くなることを混同せずに覚えていれば答えられました。問3(2)は、「くき」からの蒸散量に着目すれば求められたと思います。
[問題2]は塩酸の電気分解に関する問題でした。塩酸はHClで陽極側に塩素、陰極側に水素が発生します。酸につられて酸素にしないように。問2は7.5gまでは求めたけど、このあとどうすれば?となった人もいたのではないでしょうか?割合の問題は苦手な人が多いですよね(^_^;)ただ、他は基本問題だったのでそこで正解しておきたいです。
[問題3]は1年生の範囲である物理御三家から音の登場です。ヒントとして「太鼓をたたくと2回音がしたね」、「音が反射したんだね」という内容の会話文が与えられていました。問2は音が反射することを考えて、太鼓から校舎までの距離を2倍して計算すれば速さは求まります。問4の振動数を答える問題は、振動数=物体が1秒間に振動する回数であることを知っていないと解けない問題でした。
[問題4]は高気圧と低気圧の特徴をきちんと理解していれば、難しい問題ではありませんでした。問3(3)は記述問題は「山にぶつかり上昇し雲ができる」といった雲ができる原因を押さえられていれば、○はもらえているはずです。
[問題5]は電流の問題です。誘導電流やW=V[電圧]×A[電流]、オームの法則などを使った計算問題が出題されましたが、どれも基本的な問題だったので全問正解も難しくなかったと思います。
[問題6]は遺伝についてです。問1(1)の栄養生殖は、忘れている、思い出せなかった人が多いと予想します。定期テストでは必ず出題されるイメージですが、ここ10年間の過去問には出ていませんでした。問2の記述も正答率は低いと思いますが、それ以外は易しかったです。
[問題7]がおそらく一番難しかったのではないでしょうか?見た目で区別できない砂糖、かたくり粉、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウムの4つの物質を実験結果から判断するのですが、まず「かたくり粉」ってなんやねん?と止まった人がたくさんいたことでしょう。もちろん「かたくり粉」は知っていると思いますが、かたくり粉=でんぷんであることを知らなければ、難しかったはずです。
あとは、炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの性質の違いです。前者は水に少し溶けて、水溶液は弱いアルカリ性を示し、後者は水によく溶けて、強いアルカリ性を示すことなど区別できているか、フェノールフタレインときたらアルカリ性と判断できるかを問われる問題でした。
[問題8]は天体です。うちの生徒は問2の文章中の空欄問題で、コロナかプロミネンスかで迷って、プロミネンスを選んだのですが、( ② )の直前にしっかり「プロミネンスとよばれる炎のような~」と書いてあったのを読んでいなかったようです(+_+)
俗にいう「プロミネンス見落とし事件」ですね。
問3の計算問題は比例式を使えばすぐに求められました。問5は満月から次の満月までに約1ヵ月かかることを知っていれば簡単でした。
以上より、今年度の理科は簡単な問題と難しい問題の2極化になっていたかなと。全体でみれば、基本的な問題が多かったという印象です。